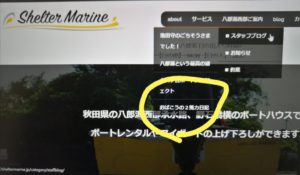ボートパーク艇庫の改修工事が始まります。
【WEST SIDE BOAT PARK】駐艇場艇庫の改修工事について

平素よりシェルターマリンウエストサイドボートパークご利用の皆様ありがとうございます。
駐艇会員さま、マリーナメンバーさま、ビジターの皆様へお知らせがございます。
お盆明けの8月17日より駐艇場にある艇庫の改修工事が始まります。今回の工事は以前から予定されていたもので工事内容は艇庫のコンクリート基礎部分の修復と艇庫全体の耐震補強工事です。


工事期間については3週間程度を予定しております。改修工事に伴い艇庫内にあった、ボートを一旦、艇庫外に出します。ご利用の皆様には大変ご不便をおかけいたしますが工事期間中はご理解ご協力の程よろしくお願い致します。

工事期間中も駐艇場は通常利用可能となっております。
八郎潟西部承水路 2020年8月3日の釣果情報
東北南部は梅雨明けしたそうなので、東北北部である八郎潟もボチボチですかね?

19時を過ぎても明るかった空も、日に日に日照時間が短くなり19時手前でも薄暗い感じになってきました。季節や時間帯によって様々な姿を見せてくれる八郎潟は本当に美しく素晴らしいです!バスフィッシングはもちろんですが、それ以外の部分でも本当に良いところですよ!
さて、水温も日に日に上昇中で、いよいよ日中は30度をマーク!それでも例年に比べると現時点ではアオコは無いと言ってもいいレベルで水質は綺麗です!ここから雨も少なくなって、気温が高い日が続くといつもの緑水に変わるんでしょうか?
釣れ方はすっかりサマー!という感じで、皆さんそれぞれのサマーパターンを探していらっしゃいます!
ハーロックガイドサービスご利用の八重樫さんは・・・
 200802_095613
200802_095613
クランクベイトでドンっ!しっかりベイトをお食べになっている本当に綺麗なバスですね!ガイドサービスならではの狙うのが難しい類のバスですが、お見事でございました!
2馬力日記オバコーさんは・・・

浚渫を極めるべく魚探がけでウロウロとしている日も多かったのですが、しっかりと自分なりの答えを見つけていらっしゃいました!半日だけでも湖上に浮くために岩手から飛んでくるガッツは中々ですね!
日野さん片村さんは・・・


1mから5mへ落ちる壁のダウンヒル!フットボールジグが炸裂して、お二人とも良いバスをキャッチしていらっしゃいました!
しかし、皆さん良いバスを釣っていますね!八郎潟の短い夏!お見逃しの無いように!
おばこうの2馬力日記のアーカイブができました!

フィールドスタッフ小原航平くんの連載ブログ「おばこうの2馬力日記」がアーカイブになりました。
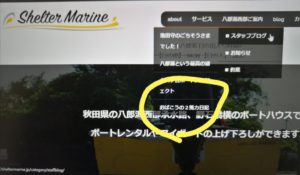
アーカイブはコチラ↓↓↓
https://sheltermarine.jp/category/staffblog/obako/
船舶免許がなくても乗れる2馬力限定仕様ボートの「ウイザード330パント」で八郎潟西部承水路をどんな風に攻略できるのか?シェルターマリンフィールドスタッフ、岩手のバスアングラー(おばこう)こと小原航平くんが西部承水路を釣りながら2馬力ボートの使い方や装備、アクセサリーを紹介してゆく企画です。船舶免許を持っていない人、持っている人も(おばこう)の連載ブログをお楽しみに!